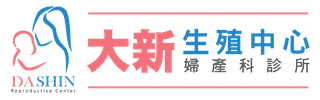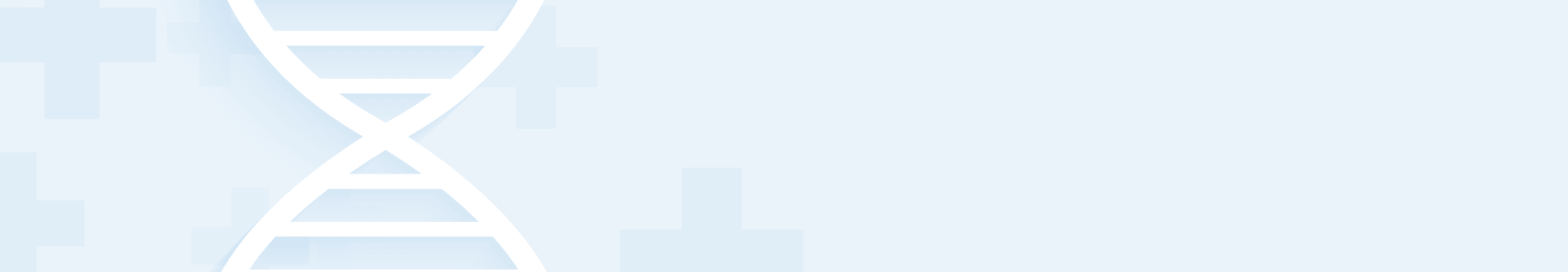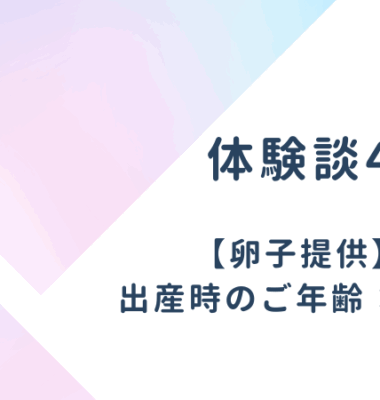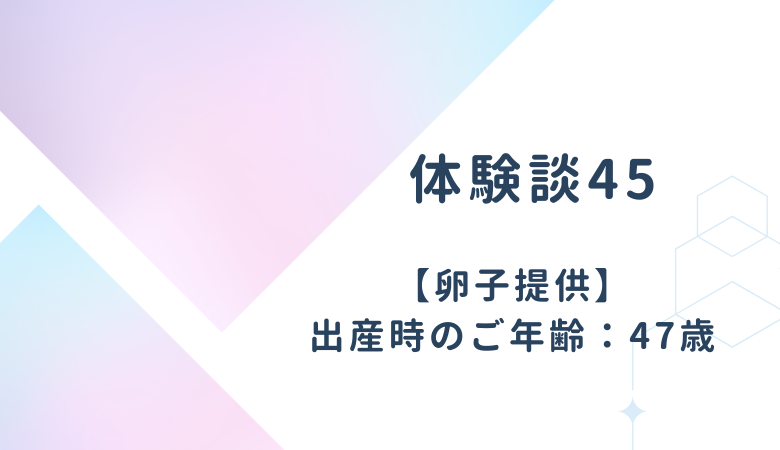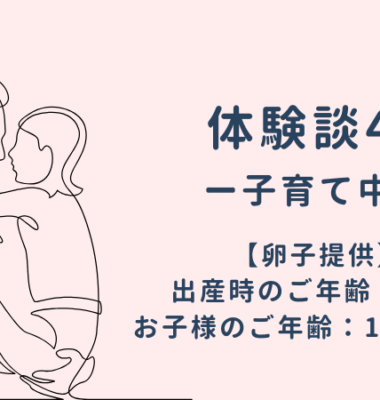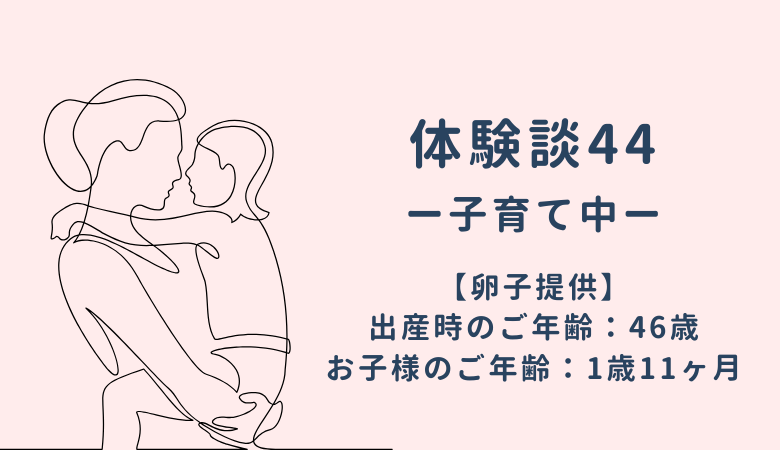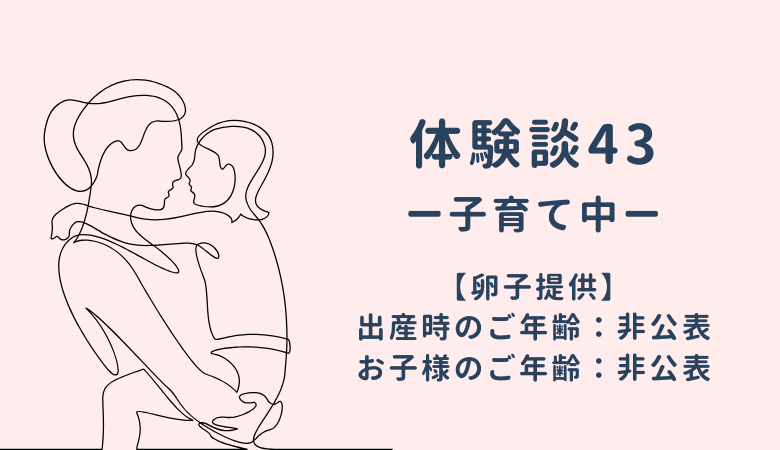特定生殖補助医療法案と台湾の人工生殖法について
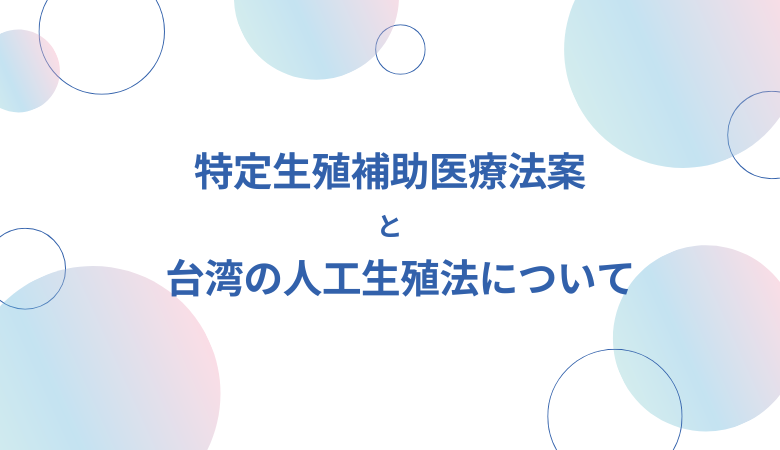
2025年2月5日に日本では、第三者の精子・卵子提供に関する特定生殖補助医療法案が国会に提出されました。
日本では長く第三者の精子・卵子提供に関する特定生殖補助医療の法制化が検討されてきたなかで、これから今回の法案の審議が進められていくということで、社会全体として理解が深まることは非常に意義のあるものであると考えています。
当院は2016年頃から海外在住の方への治療の受け入れをはじめ、2019年には国際医療機関として台湾の衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)にも認定をいただき、国内外で当院の取り組みを発表させていただくことも増えてきました。
これまでの当院の経験を踏まえ、少しでも情報としてお役に立てればと思い、今回書かせていただいております。
子どもを授かりたいと願う多くのご夫婦がいらっしゃいます。
長く不妊で悩むご夫婦、一度は子どもをもつことを諦めたもののどうしても願いを捨てきれないご夫婦、若いときの病気の治療で自分の卵子では子どもを授かることができないご夫婦。
子どもを授かり、自らの家族に命を繋いでいきたいと思うことは、人間としての根源の考えであるものです。
また同時に、そしてそれ以上に、生まれてくる子ども自身がもつ権利が大事であり、ときには難しい問題でありながらも、今回の法案でそうした議論を深めていくことは社会において大きな価値があるものといえます。
台湾では生殖医療を規定する人工生殖法という法律が1999年に施工され、2007年の改正によって第三者による卵子提供や精子提供に関してドナーの情報保護も含めた規定が定められました。
これにより国が管理をしながら、商業目的にならないよう配慮がされた形で、不妊で悩む夫婦が第三者による卵子提供・精子提供を、適切な管理の元で受けられるようになりました。
当院も、人員要件や設備要件、倫理委員会の設置や、審査を経て、台湾の衛生福利部の認可を受け、卵子提供や精子提供を含む生殖補助医療を安全かつ効果的に提供できることとなっています。
そして、日本をはじめ、海外からも不妊に悩む多くのご夫婦にお越しいただき、お一人お一人に適切な治療を安心の体制で提供できるように日々努めています。
卵子提供や精子提供に関しては申請者一人ひとりに対して、台湾の行政機関である衛生福利部の審査を受けるものとなります。行政機関との相互の信頼関係を築き、適切な申請を行うことで安心かつ安全な状態を作ることが大切であり、当院としても適切な緊張感をもって正しい申請業務をおこなっています。
卵子提供や精子提供を規定する台湾の人工生殖法には細かな内容がありますが、日本人の治療者の多い卵子提供を中心に、人工生殖法の内容をご紹介させていただきます。
卵子提供ドナーの条件としては、原則として20歳以上、40歳未満の健康な女性であるとされ、遺伝性疾患の有無や精神的・身体的健康状態が評価されます。
当院としては、年齢は30歳までという条件を設け、遺伝性疾患や感染症疾患などを含め、数多くの検査を事前に実施し、適切なドナーのスクリーニングを行っています。
台湾の人工生殖法第19条では、ドナーは報酬を受け取ることはできませんが、「卵子の提供によって生じた必要費用」として医療機関が最大99,000台湾ドルを支払うことができることとなっています。
なお、この栄養費は、金銭的な補助・実費補償を指し、報酬ではなく補償金として位置付けられています。
そして今回日本の法案においても議論点となっている、ドナー本人の情報についてですが、台湾においては卵子の提供者と受け手の双方に匿名性が守られることとなり、提供者の身元は開示がされません。
子どもが成人しても原則として提供者の身元を知る権利は認められていません。
ドナーの情報を確認ができるのは、当院のような認定を受けた医療機関に限られており、原則受け手に伝えることのできるものは、人種、皮膚の色、血液型、まぶた(一重 or 二重)についてとなります。
ただし、卵子提供の受け手となる治療者が、その先に安心して子どもを生み育てられるよう、事前に希望する方からは治療者本人である奥様の写真を提供いただき、当院側でのドナーの選定判断に使用させていただいています。
また、当院のドナー担当者の主観に伴いますが、ドナーの性格の印象や、趣味など、ドナー本人にも了承を得ながら、個人情報を守りながら伝えられる範囲での情報をお伝えするようにしています。
こうした情報は、今後治療者が子どもを生み、育てるうえで大事な情報であるという考えからです。
これらを治療者に伝え、ドナー決定をするかの判断をいただくこととなっています。
台湾において、卵子提供ドナーとなれるのは自分の子ども以外の他者では1人のみという定めがあり、医療機関からの申請をしてから衛生福利部において確実な確認が行われます。
衛生福利部の倫理審査委員会による審査を経て許可が出され、はじめてドナーによる卵子提供を行うことができるようになります。
また、出産後には、「出産日」「妊娠日数」「出産時の子の体重」「性別」「出産方法」などの細かな情報を衛生福利部に適切に報告する義務があります。
このようにして、台湾の行政機関である衛生福利部への申請や双方向での連絡を行いながら、卵子提供の治療者お一人お一人に対して許可を受け、治療を行うこととなっています。
日本での議論もさらに深まっていくことと思っていますので、台湾では2007年から改定・施工された人工生殖法についての説明として今回書かせていただきました。
国の背景や考えのポイントなど異なるものがあるとは思いますが、少しでも参考になれば幸いです。
大新生殖医療センター Dashin Reproduction Center
院長 陳 志宏